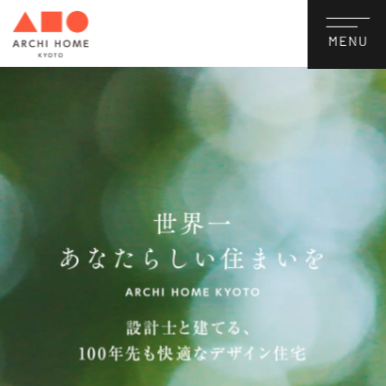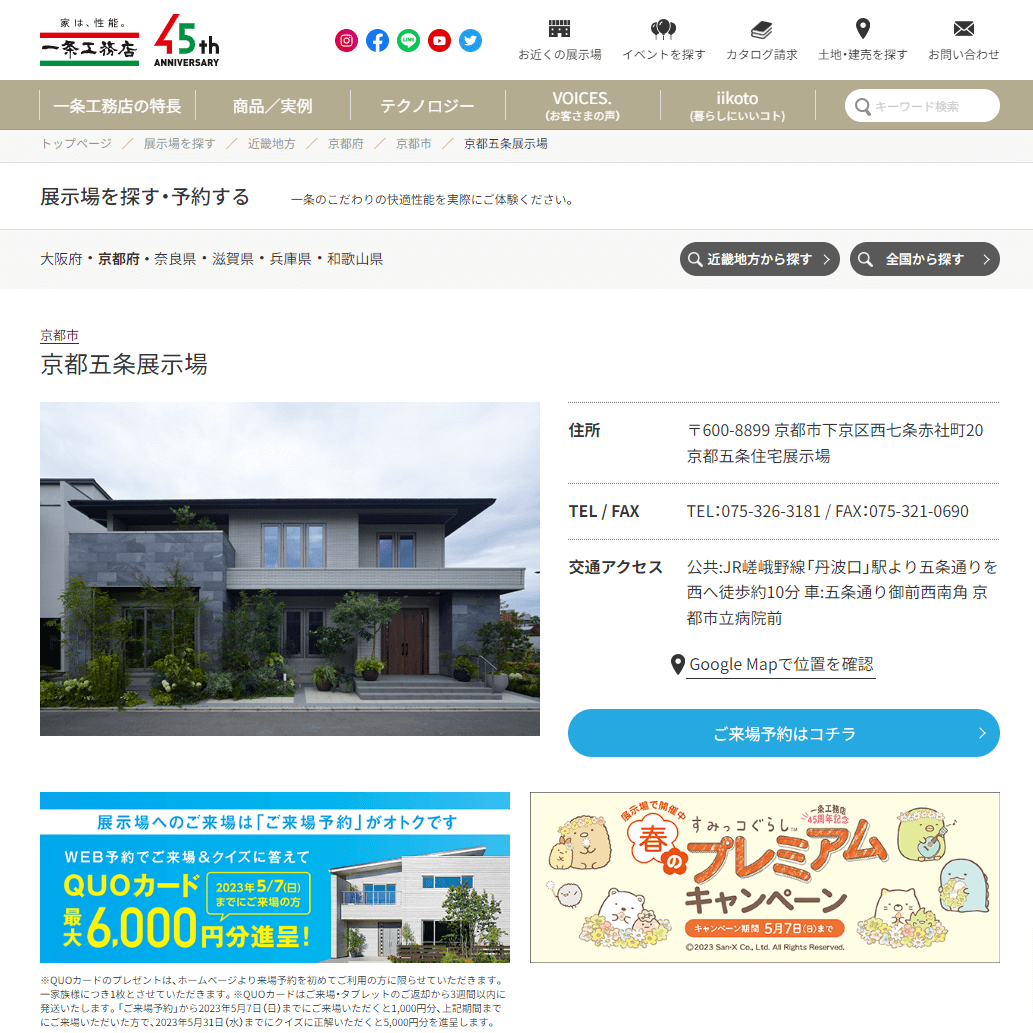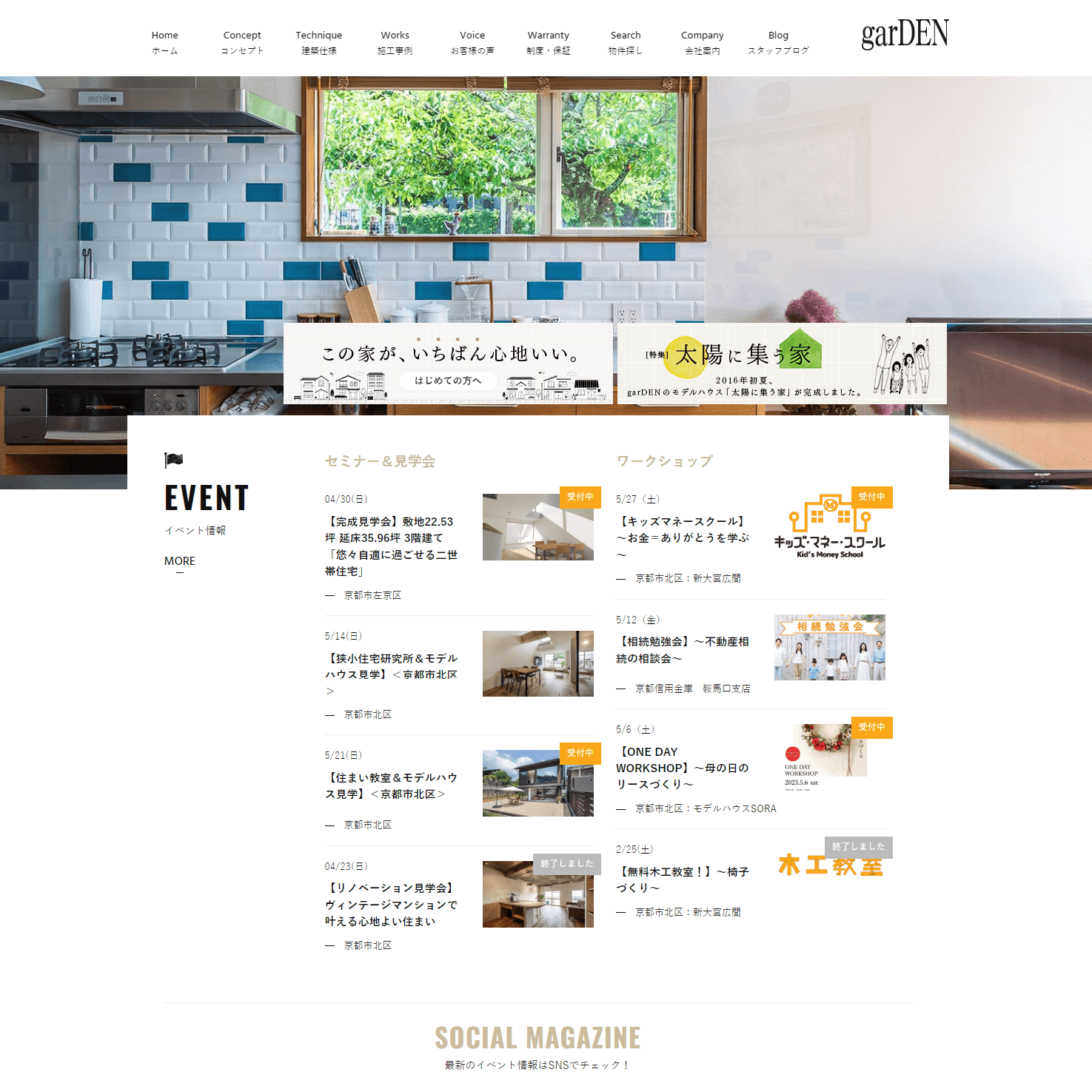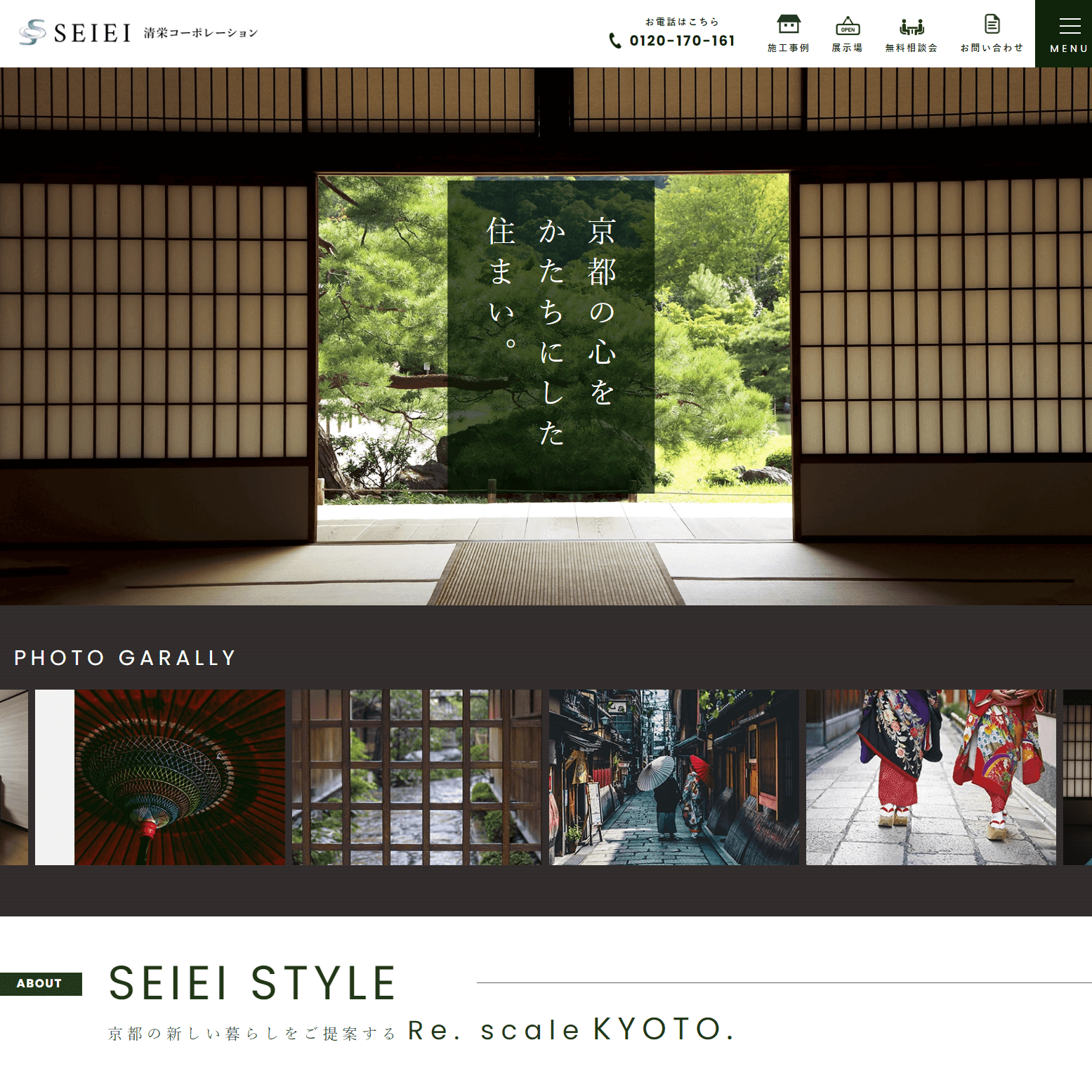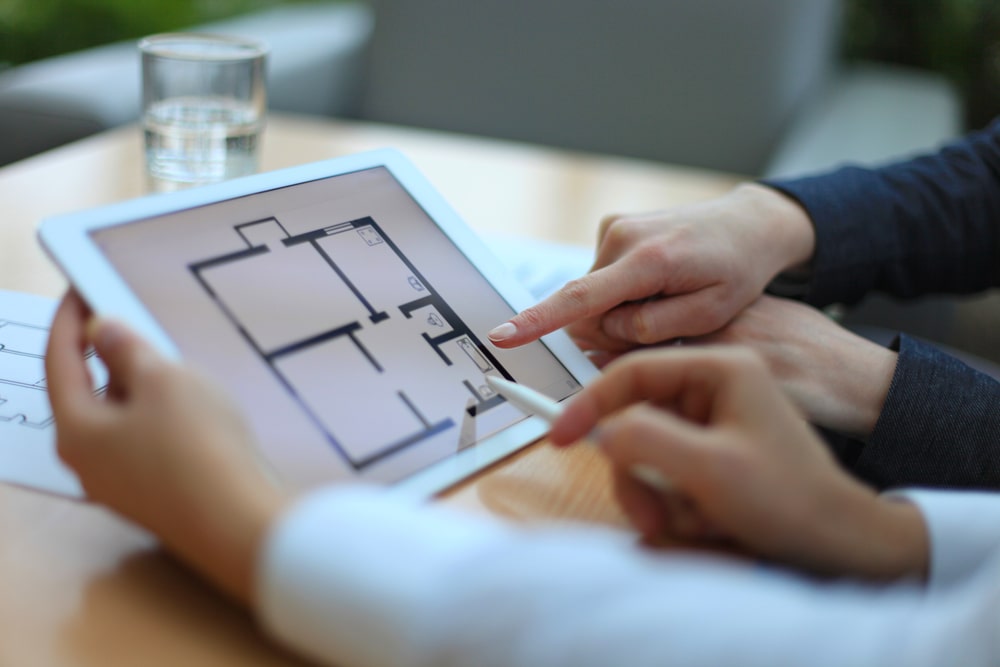注文住宅を建てる際の懸念点として「地震に対する備え」があります。近年の世間における防災に対する関心の高まりから、新しく家を建てる際「耐震等級3」を検討する人が増えているのです。そこで本記事では、耐震等級の概要と、耐震等級3の注文住宅のメリット・デメリットについて詳しく解説します。
耐震等級とは
耐震等級とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が定める「住宅性能表示制度」に基づく住宅の耐震性能の指標で、等級1〜3の三段階で示されます。取得は任意で、指定機関の審査を受けて「住宅性能評価書」が交付されることで認定されます。
一方で耐震基準は建築基準法によって定められた、住宅建築時に必ず満たさなければならない最低限の基準です。現行の耐震基準(2000年6月1日施行)を満たす家は耐震等級1に相当しますが、審査を受けない限り正式に耐震等級1と認定されることはありません。
耐震等級1は、震度6強程度の地震でも倒壊しないレベルの性能で、現行の建築基準法を満たす住宅が該当します。耐震等級2は等級1の1.25倍の耐震性を持ち、学校や病院などの公共施設や、長期優良住宅の基準となっています。
耐震等級3は等級1の1.5倍の耐震性を持ち、災害時に復興拠点となる警察署や消防署などに求められる最も高い基準です。耐震等級が高いほど構造は強固になり、設計や施工の精度もより厳密に求められます。
耐震等級3の注文住宅のメリット
ここからは、耐震等級3の注文住宅を建てるメリットについてみていきましょう。
地震による被害を抑えられる
耐震等級3の家を建てる最大のメリットは、地震による被害を最小限に抑えられる点です。等級1では震度6強の地震において倒壊を防ぎ命を守ることはできても、損傷が大きく住み続けられないケースがあります。
一方で、耐震等級3の家は構造がより強化されており、地震後も建て替えを必要とせず、そのまま住み続けられる可能性が高くなります。これにより、避難生活を余儀なくされるリスクが低下し、家族の精神的な負担も軽減されることでしょう。また、資産としての価値も維持しやすくなります。
金利・保険料の優遇措置がある
さらに、経済面でもさまざまなメリットがあります。例えば、耐震等級3の住宅は金融機関によって住宅ローンの金利が優遇されることが多く【フラット35】Sなどの制度を利用すれば、住宅性能に応じて金利が0.25〜0.5%下がる可能性があります。
これは、長期的に見て大きな節約になることでしょう。また、地震保険においても耐震等級によって保険料の割引があります。耐震等級1で10%、等級2で30%のところ、等級3では最大50%の割引を受けられます。
建築基準法に適合している住宅は等級1とみなされ、建築確認済証と完了検査済証があれば10%の割引が可能です。そして、耐震等級3ではその割引率がより大きくなります。
資産価値につながる
さらに、耐震等級3の住宅は売却時にも強みがあります。高い耐震性能が証明されていることで、資産価値が評価され、高値で売却できる可能性があります。ただし、最近では中古住宅を安く購入してリノベーションする志向も強まっており、価格が高すぎると購入希望者に敬遠されるリスクもあるため注意が必要です。
耐震等級3の注文住宅のデメリット
耐震等級3の住宅を建てる際には多くのメリットがありますが、その一方でデメリットや注意すべき点もいくつか存在します。
建築コストの増加
まず大きなデメリットとして挙げられるのが、建築コストの増加です。耐震等級を上げるには使用する建材の量が増え、設計や施工の手間も増すため、人件費も高くなります。
さらに、木造住宅では耐震等級1であれば2階建てまで構造計算が不要ですが、等級2以上では構造計算が義務となり、その費用が20〜30万円程度かかるのが一般的です。
加えて、等級3として認定されるには第三者機関による評価が必要となり、設計や工事の期間も通常より延びる傾向があります。具体的には設計に5〜6カ月、工事に6カ月かかるところが、耐震等級3にするとそれぞれ1カ月ずつ長くなり、仮住まいの家賃負担も増加する可能性があります。
家の広さに制限がかかる可能性がある
また、建築コストの増加により、希望していた家の広さを確保できない場合もあります。たとえば、耐震等級1なら建てられた30坪の住宅が、等級3では予算の都合上25坪に縮小されるケースがあります。
さらに、耐震性を確保するために耐力壁を増やす必要があるため「広いリビングが欲しいのに中央に壁を設けなければならない」といった間取り上の制限も発生するかもしれません。
建築以来の段階で明確に希望を伝えなければいけない
さらに注意したいのは、耐震等級3は任意制度であるため、建築を依頼する段階で明確に希望を伝える必要があるという点です。耐震等級3を前提とした設計でなければ、後から等級3の認定を希望しても設計や工事を一からやり直さなければならず、進行状況によっては変更が不可能な場合もあります。
耐震等級3を検討しているなら、できるだけ早い段階で設計者や施工会社と相談することが重要です。なお、認定のための第三者機関への申請は、自身で行っても建設会社などに依頼しても構いません。
まとめ
注文住宅を建てる際、地震に強い家づくりを重視する方にとって「耐震等級3」は非常に有力な選択肢です。震度6強クラスの地震でも建物の損傷を最小限に抑えられるため、安心して長く暮らすことができます。また、住宅ローン金利や地震保険の割引など、経済的な優遇も大きな魅力です。資産価値の維持にもつながる点は将来の売却時にも有利です。一方で、建築費の増加や間取りの制約、早期の意思表示が必要など注意点もあります。地震に備えた後悔のない家づくりのために、耐震等級3の特徴をしっかり理解し、設計段階から計画的に進めることが大切です。